発達障害、不登校、家庭崩壊、対人恐怖、
自分や家族が抱えるさまざまな問題を乗り越え、
絶望の中から見つけ出した
幸せになるための統合解決の心理学で
家族を救い、勇気を与える人になる
理解からはじまる子育てコーチング

発達障害、不登校でも大丈夫!
お子さまの発達や登校に悩むお父さんお母さんを応援します。子どもの特性を理解し、適切な関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、お子さまの成長をサポートできます。一人で抱え込まず、新しい子育ての可能性を一緒に見つけましょう。
.
.
子育ての悩みは解決できます
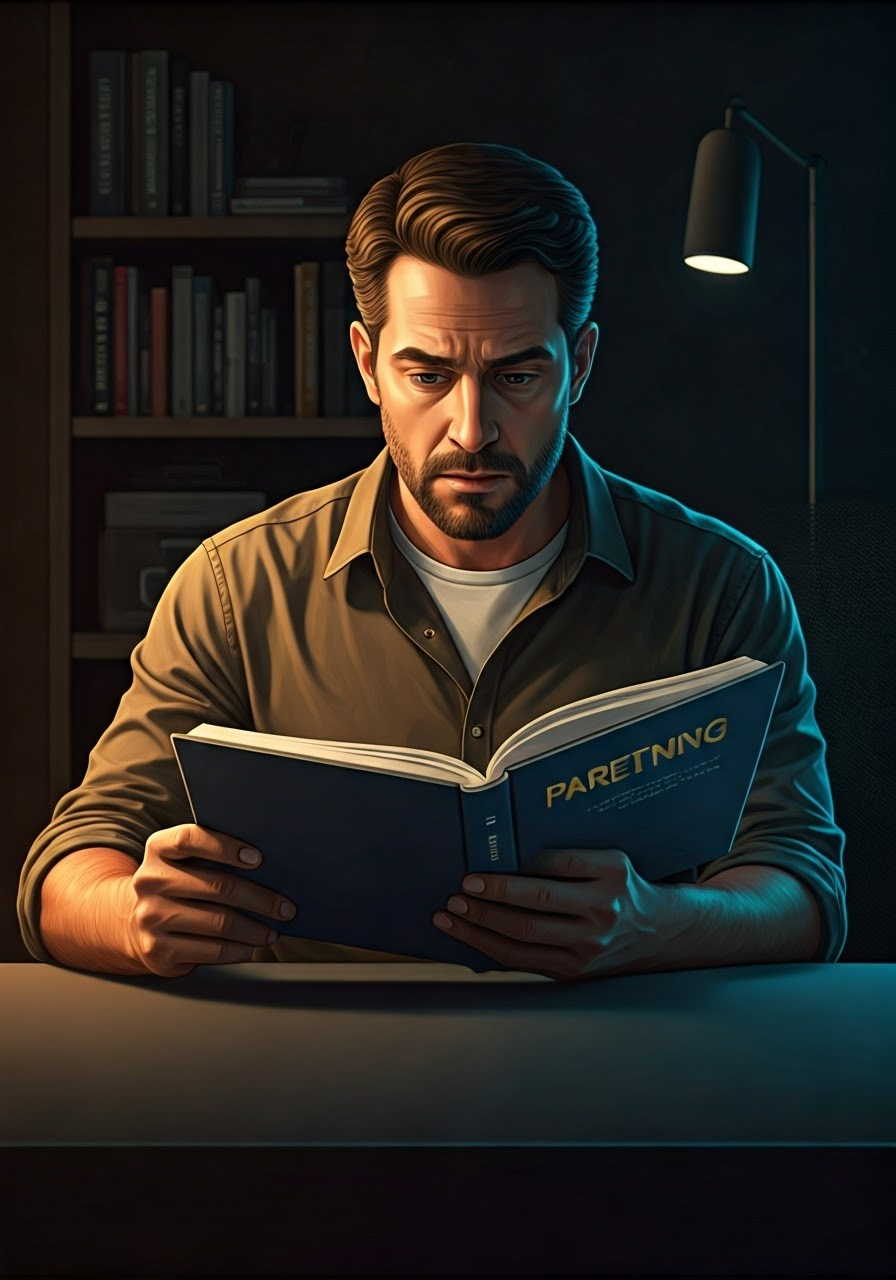
ひとりで抱える悩み
現代社会では、子育ての悩みや葛藤をひとりで抱える親が増加しています。仕事と家庭の両立、子どもとの接し方など、様々な課題に直面しています。
学ぶ意欲の高まり
誰もが子育てに悩む時代だからこそ、親が積極的に学ぶ意欲が高まっています。正解のない子育てだからこそ、学び続けることが大切です。
不安解消の実例
コーチングを取り入れることで、子どもとの関係が改善し、不安が解消された事例が増えています。小さな変化が大きな成果につながります。
発達障害・不登校の現状と向き合う
6%
発達障害診断率
国内での発達障害の診断率は年々上昇しており、現在約6%前後と言われています。決して珍しいものではありません。
30万人
不登校の子ども
2023年度の文部科学省統計によると、不登校の子どもは約30万人に達しています。この10年で大きく増加しています。
100%
理解の必要性
社会全体で発達障害や不登校に対する柔軟な対応と理解が求められています。一人ひとりの特性に合わせた支援が必要です。
子供と向き合う時には100%味方でいてあげる気持ちが大切です。
子どもに届く関わりかた
特性を理解し、否定せずに聴く
お子さまの特性を理解し、否定せずに話を聴く姿勢が重要です。言葉だけでなく、気持ちや背景にも注目しましょう。
安心できる居場所づくり
解決を急がず、まずは安心できる居場所をつくりましょう。お子さまが「ありのままでいい」と感じられる環境が成長の土台になります。
現実的な目標設定
「普通」を押し付けず、お子さまの状態に合わせた現実的な目標を設定しましょう。小さな成功体験が自信につながります。
親が知っておきたいコーチングスキル
傾聴力
お子さまの話を遮らず、最後まで聴き切る姿勢が重要です。うなずきや相づちで「聴いている」ことを伝えましょう。話を聴くだけでお子さまの心は軽くなります。
受容の態度
良い悪いで判断せず、まずは「理解」に努めましょう。お子さまの行動には必ず理由があります。その背景を知ることで適切なサポートができるようになります。
質問力
「なぜ」ではなく「どんな」「どうしたら」といった開かれた質問で、お子さまの気持ちや考えを引き出す会話を心がけましょう。子ども自身が答えを見つける手助けをします。
成功体験のサポート
小さな成功体験を積み重ねるサポートをしましょう。達成感は自己肯定感を高め、次の挑戦への勇気につながります。
失敗を恐れない子育て実践例

口出しを減らし信頼感UP
常に指示や指摘をしていた親が、子どもの判断を尊重するようになったところ、子どもから相談されることが増え、信頼関係が深まりました。
関わり方の変化
成績や結果ではなく、「プロセス」や「努力」を認めるようになったことで、子どもが自分から学習に取り組むようになったケースがあります。
小さな成功の積み重ね
小さな挑戦とその成功を一緒に喜び合うことで、子どもの自己肯定感が高まり、次の挑戦へのモチベーションにつながった事例が多く報告されています。
専門家・第三者のサポート活用法
専門家への相談
プロのカウンセラーやコーチへの相談で、親の心理的負担を軽減できます。客観的な視点からのアドバイスが新たな気づきをもたらします。
相談窓口の活用
「ひとりで抱え込まない」ための相談窓口や地域のイベント情報を積極的に収集し、必要なときに躊躇なく活用しましょう。
多様な居場所
学校以外の居場所(フリースクールや地域の支援団体)も積極的に選択肢に入れましょう。お子さまに合った環境を柔軟に考えることが大切です。
親の会・交流会
同じ悩みを持つ親同士の交流会や親の会に参加することで、共感と具体的な情報を得られます。孤独感の軽減にも効果的です。
親が一歩踏み出すために

親子の未来は広がる
小さな行動の積み重ねが、親子の可能性を広げます
家族みんなの安心
親の理解と変化が家族全体の安心につながります
誰でも始められる
コーチングは特別なスキルではなく、今日から実践できます
親の小さな変化が、お子さまと家族全体に大きな影響を与えます。
完璧を目指さず、まずは「聴く」ことから始めてみませんか?
一歩踏み出す勇気が、新しい親子関係の第一歩です。
公式LINEから30分の無料面談をお申込みいただけます。
ご希望の方は下のバナーをクリックしてご登録ください。
新着情報
-
 2026.01.25
2026.01.25
ヒントは目の前
いちばんの答えを、いちばんに外してるから解決しない何かがうまくいかないとき、「どうしてこんなに頑張っているのに…」そう思ってしまうことがあります。実はその裏側には、“ほんとうの答えを自…
-
 2026.01.24
2026.01.24
ここにいていいよ
「自分には価値がない」と思ってしまうと、生きるのが苦しくなる「自分には価値がない」そう思い続けていると、どんな出来事も悪い方に解釈してしまい、生きることそのものが重たくなってしまいます。…
-
 2026.01.23
2026.01.23
迷惑でしょうが
他人に迷惑かけずに生きたい?それは無理ですね。「他人に迷惑をかけないように生きなきゃ」そう思って頑張りすぎて、苦しくなっていませんか?結論から言うと――人に迷惑を一切かけずに生きるなん…
-
 2026.01.22
2026.01.22
早起きして歩いてみると
朝のウォーキングは「脳のメンテナンス」ゆっくり歩くだけで心が整う理由朝の空気には、どこか特別な清々しさがあります。深呼吸をしただけで、体の中を新しい風が通り抜けていくような感覚になるこ…
-
 2026.01.21
2026.01.21
やりたいと思ったら、それが合図、人生が変わる瞬間
風が吹く波が立つ 思いつくとき、それは“神さまのサイン”ふと、胸がざわっと動く瞬間ってありませんか。「これ、やってみたいな」「なんだか分からないけど気になるな」そんな“風”のような小…
-
 2026.01.20
2026.01.20
生きる覚悟
もう逃げない。腹をくくる。どんな結果も受け止めて、自分を生きるんだ人生には、思い通りにいく日もあれば、どうしても前に進めない日もあります。苦しかったり、迷ったり、不安が押し寄せた…
-
 2026.01.19
2026.01.19
チャンスのつかみかた
結局は「決断と勇気」人生には、何度もチャンスがあります。それは、キラキラした形で現れるとは限りません。むしろ多くの場合、「苦しい」「もう限界かもしれない」そんな状況の中で、ひっそ…
-
 2026.01.18
2026.01.18
できることをやらない
できるけど、やりたくないこともやめよう「できるから、やっている」そんなこと、ありませんか?長く生きていると、いろいろな経験を積み、いろいろな仕事ができるようになります。やろうと思えばで…
